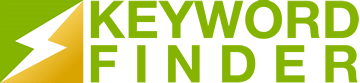XMLサイトマップを自動生成するWordPressのプラグイン“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”を使用していますか?
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”とは、検索エンジンにブログ内の重要なページを中心にクロールしてもらうために役立つsitemap.xmlを自動生成してくれるWordPressの数多く存在するプラグインのひとつです。
※sitemap.xmlはクローラーに対して強制力はありません。
もちろん“sitemap.xml”は手動でも更新可能ですが、更新性が高いとあまりにも手間なので、こういったプラグインを導入して自動更新にしておくと後々の管理としても大変便利です。
ちなみに今回ご紹介するのは検索エンジン向けにクロールのヒントとなるsitemap.xmlを自動生成してくれるWordPressのプラグインのことであって、検索ユーザー向けのHTMLサイトマップページとは異なります。
また、こういったプラグインは様々公開されていますが、中でも“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”は未だ定期的に更新されていて、セキュリティ面でも安心でき、sitemap.xmlを自動生成してくれるのはもちろん、インストール後の設定なども非常にシンプルで使いやすいため、導入している方も多いのではないでしょうか?
シンプルとは言っても除外したいカテゴリーや個別記事も指定でき、sitemap.xmlを作成するにあたって必要な項目は備えられているので、構造上困ることもなく、SEOを考慮して設置しておきたい要素のひとつです。
では今回は、クローラーに対してページの一覧を優先度や更新頻度などと併せて記述するsitemap.xmlを自動生成してくれるWordPressのプラグイン“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”のインストールから作成方法、設定方法について詳しくご説明していきます。
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)とは?

“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”とは、検索エンジンのボット(クローラー)がページを巡回する際のヒントとして読み取るsitemap.xmlを自動生成してくれる便利なWordPressプラグインで、一度インストール・設定しておくだけで後は自動更新され、それを定期的にクローラーが読み取ってくれるという非常に便利なプラグインです。
そして、このsitemap.xmlは、ブログ内の重要なページ(クロールしてほしいページ)を記述しておくことによって効率良く巡回し、強制力はないもののクローラーの最適化にもなる重要なファイルです。
サイトマップファイルのポイントとしては、クロールする必要がないページ、いわゆる質の低いページや以下のような検索結果に表示される必要のないページを除外しておくことが大切で、“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”でもそういった設定は可能ですので、無駄なクロールを制御しておくべきです。
- 申込みページ
- お知らせページ
- ランディングページ(LP)
ただし、先ほどもご説明した通りsitemap.xmlはクローラーに対して強い指示を課すものではありませんので、本当にクロールしてほしくないページには“noindex”の付与や、コンテンツとして質が低いのであれば削除・統合・リライトなどの施策が必要となってきます。
要は、質の高いページだけを公開しておくことが理想で、そういったページが追加されたタイミングで“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”がsitemap.xmlを自動更新していくというわけです。
もちろんクローラーが最適化され、重要なページを中心にクロールすることによって、部分的に修正した箇所などが素早く反映されることにも繋がるでしょうし、新規投稿した際にも役立ちます。
この辺りは、キャッシュを利用している場合だとなかなか情報が更新されないケースも珍しくありませんので、定期的にキャッシュの削除や、新規の記事投稿した際や情報の更新をなるべく早く反映したい場合はgoogleサーチコンソールの「URL検査」から“インデックス登録をリクエスト”を利用すると良いでしょう。
さて、先ほどからXML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)と記載していますが、
「Google XML Sitemaps」は、2020年に「XML Sitemaps Generator for Google」へと名称が変更されました。
この名称変更の主な理由は、Google以外の検索エンジン(BingやYahoo!など)にも対応していることや、より汎用的なXML形式のサイトマップ生成ツールであることを明確にするためと言われています。
また、Googleの公式なプラグインと誤解されることを避ける意図も含まれています。
開発状況についても、現在も定期的にアップデートが行われており、WordPressの最新バージョンへの対応やセキュリティ面の強化、新機能の追加などが継続的に実施されています。
そのため、安心して利用できるプラグインとして、多くのユーザーに支持され続けています。
公式のプラグインページでも、更新履歴やサポート情報が随時公開されていますので、導入前に一度確認しておくと良いでしょう。
サイトマップインデックスとは?その必要性
サイトマップインデックスとは、複数のサイトマップファイルをまとめて管理するための「目次ファイル」のことです。
通常、サイトマップ(sitemap.xml)はウェブサイト内の全ページURLをリスト化したXMLファイルですが、ページ数が多い大規模サイトや、投稿・固定ページ・カテゴリごとにサイトマップを分割したい場合、1つのサイトマップファイルだけでは管理が難しくなります。
このような場合に活用されるのが「サイトマップインデックス(sitemap_index.xml)」です。
サイトマップインデックスは、複数の個別サイトマップ(例:投稿用、固定ページ用、カテゴリ用など)へのリンクを一覧で記載したXMLファイルで、検索エンジンのクローラーに対して「どのサイトマップが存在するか」を効率的に伝える役割を果たします。
たとえば、以下のような構造になります。
<sitemapindex> <sitemap> <loc>https://example.com/sitemap-posts.xml</loc> </sitemap> <sitemap> <loc>https://example.com/sitemap-pages.xml</loc> </sitemap> <sitemap> <loc>https://example.com/sitemap-categories.xml</loc> </sitemap></sitemapindex>
このように、サイトマップインデックスを利用することで、検索エンジンは各サイトマップファイルを効率よく巡回でき、サイト全体の構造や更新情報を正確に把握しやすくなります。
特にページ数が多いサイトや、コンテンツの種類ごとに管理したい場合には、SEOの観点からも非常に有効な仕組みです。
サイトマップインデックスファイルがSEOの観点から必要とされる理由は、主に大規模なウェブサイトや多くのページを持つサイトにおいて、検索エンジンのクローラーが効率的に全ページを把握・巡回できるようにするためです。
通常のsitemap.xmlファイルにはURLの上限(Googleの場合は最大50,000件、またはファイルサイズ50MBまで)がありますが、これを超える場合や、投稿・固定ページ・カテゴリ・タグなど複数の種類のサイトマップを分割管理したい場合に「サイトマップインデックス」が役立ちます。サイトマップインデックスは、複数の個別サイトマップファイルへのリンクをまとめた“目次”のような役割を果たし、クローラーに対して「どのサイトマップを優先的に巡回すべきか」「どのような構造でページが存在するか」を明確に伝えることができます。
これにより、以下のようなSEO上のメリットが得られます。
- クローラーが効率よく全ページを発見・インデックスできる
- 新規追加や更新されたページが素早く検索エンジンに認識されやすい
- サイト構造が明確になり、重要なページやカテゴリごとに優先度や更新頻度を細かく設定できる
- 大規模サイトでもサイトマップの管理・運用が容易になる
特にECサイトやニュースサイト、メディアサイトなどページ数が多い場合は、サイトマップインデックスの導入が推奨されます。Google Search Consoleでもサイトマップインデックスの送信が可能で、検索エンジンへの最適な情報提供につながります。
このように、サイトマップインデックスはSEO対策の基礎として、検索エンジンにサイト全体の構造を正しく伝え、インデックスの最適化を図るために非常に重要な役割を担っています。
XML Sitemaps Generator for Googleの設定について

さて、“XML Sitemaps Generator for Google”は、基本的にプラグインを管理画面もしくは手動でサーバーにアップロード、インストールして“有効化”し、簡単な設定のみでsitemap.xmlを作成することができます。
※手動でアップロードする際は、「Google XML Sitemaps – WordPress プラグイン | WordPress.org 日本語」からファイルをダウンロードしてください。
他にもsitemap.xmlを作成する有名なプラグインは“All In One SEO Pack”や“Yoast SEO”などがあり、既にそちらを利用している方は、“XML Sitemaps Generator for Google”をインストールする必要もないでしょう。但し、“All In One SEO Pack”や“Yoast SEO”には画像サイトマップや動画サイトマップの生成機能が備わっている場合があります。
また、“XML Sitemaps Generator for Google”の設定画面としては、下記のような項目がありますが、基本は“有効化”するだけで十分sitemap.xmlとして機能します。
- 基本的な設定
- Additional Pages(WordPress外で公開されているページを含めるかどうかの設定)
- 投稿の優先順位
- Sitemap コンテンツ
- Excluded Items(含めないカテゴリーや記事)
- Change Frequencies(更新頻度の設定)
- 優先順位の設定 (priority)
sitemap.xml自体、基本はどういったページが存在するのか?urlや重要度、更新頻度や最終更新日などを記載するファイルなので、これによってSEO順位の上昇に直結するものではありません。あくまでクローラーの最適化・重要なページを中心に巡回してもらうための手段として認識しておくと良いでしょう。
プラグインのインストール
プラグインを利用するにはまず、お使いのWordPressに「Google XML Sitemaps」をインストールする必要があります。
管理画面の「プラグイン」>「新規追加」から“Google XML Sitemaps”で検索します。
※ここではGoogle XML Sitemapsの検索・インストールを例にご紹介します。名称が変更されているのでXML Sitemaps Generator for Googleで検索をお試しください。

そして“今すぐインストール”をクリックして、終了後に“有効”にて完了となります。(設定画面は、WordPress管理画面の「設定」>「XML Sitemap」をクリックします。)
この状態ですでに使用できるわけですが、今回はこの“Google XML Sitemaps”がどのような機能を兼ね備えているのか?使い方や設定などを各項目ごとにご説明していきたいと思います。
基本的な設定
“基本的な設定”の項目では以下の内容が表記されています。
- 通知を更新
- 高度な設定

この“通知を更新”の3つの項目では、まずGoolge・Bingに通知するかどうかのチェック、そして“サイトマップのURLを仮想robots.txtファイルに追加”ではサイトマップの場所を検索エンジンに伝えることができるため必ず3つともチェックを入れておきます。
デフォルトですでにチェック済みです。
続いての“高度な設定”では、主にサイトマップの圧縮やサイトマップの場所についての設定となります。
まず、“Try to automatically compress the sitemap if the requesting client supports it.”と記載されている項目では、記事数が多い場合ファイルサイズを圧縮するかどうかの設定で、こちらもデフォルトではチェックが入っているので、そこまで気にする必要もありません。
次の“XSLTスタイルシートを含める”ではサイトマップを読みやすくするための“sitemap.xsl”を読み込むかどうかの設定で、特に必要なければ“デフォルト設定を使用”にチェックしておいて構いません。
また、“Override the base URL of the sitemap”では、WordPressをルートディレクトリ以外(サブディレクトリ)にインストールしている場合、インストールディレクトリを入力して、下記のタグを“.htaccess”に追記することによってルート(トップレベルディレクトリ)に置いたサイトマップを書き換えることが可能となります。
<IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine OnRewriteRule ^sitemap(-+([a-zA-Z0-9_-]+))?.xml(.gz)?$ /blog/sitemap$1.xml$2 [L]</IfModule>
最後の“HTML形式でのサイトマップを含める”と“匿名の統計を許可する”は、特にサイトマップとしての効果とは関係ありませんので、チェックする必要はありません。
Additional Pages(WordPress外で公開されているページを含めるかどうかの設定)
続いての項目では、WordPressと静的サイトを混合させて運営している場合(サイトの一部がWordPress)、“Google XML Sitemaps”ではWordPressで管理するページしかサイトマップにページを記述・更新していかないため、クロールしてほしい重要なページは手動で追加する必要があります。

そういったページを以下の項目とともに設定していきます。(クロールの必要があるページのみ)
- 優先順位の設定(priority)
- 更新頻度の設定(changefreq)
- 最終更新日
特に、メインとなる製品やブランドなど各自社サイトは必ずしもWordPressで管理する必要もありませんから、ブランド価値を高めるデザインや工夫を重要視し、自社で管理するオウンドメディアとしてWordPressを活用しているという企業も多いのではないでしょうか?そういった場合、サイトマップを自動で更新していくために必要な項目で、もし必要であれば重要なページを追加登録しておくと良いでしょう。
もちろん全てをWordPressで管理し、トップページのindex.phpをカスタマイズすることも可能ですが、その場合テーマのアップデートによって元に戻ってしまうといった問題が出てきますので、フルカスタムでトップページを用意したい場合などはWordPressと切り離して作成するべきです。
こういった理由からサブディレクトリにWordPressをインストールしているケースが多く見受けられるというわけです。
投稿の優先順位
ここでの設定では、sitemap.xmlに記載する個別ページの優先順位(priority)の算出方法を決めます。
そもそもsitemap.xmlには、0.0〜1.0の間でクローラーへ個別ページごとに優先度を伝えることが可能です。
それによってクロールの頻度・巡回のヒントとなり、クローラビリティとしての要素となるため、SEO効果としては低いかもしれませんが、重要なページは優先順位を高く設定しておくべきです。
ここでは以下の項目が並び、個別ページ毎に優先順位を変更するかどうかを設定します。
- 優先順位を自動的に計算しない
- コメント数
- 平均コメント数

ちなみにデフォルトでは“コメント数”にチェックが入っていますが、ここでは“優先順位を自動的に計算しない”に変更しておくと良いでしょう。(後ほど0.0〜1.0までの優先度を指定することができます。)
Sitemap コンテンツ
続いての“Sitemap コンテンツ”では、sitemap.xmlに含めるページタイプを指定していきます。

項目としては、“WordPress標準コンテンツ”・“カスタムタクソノミー”・“カスタム投稿タイプ”からsitemap.xmlにページを含めるかどうかを設定し、デフォルトでは以下の3点のみチェックが入っている状態となっています。
- ホームページ
- 投稿 (個別記事) を含める
- 固定ページを含める
中でも固定ページは検索結果に表示される必要のないプロフィールページや購入・登録フォームなども含まれていますので、クロールの必要がなければ適宜チェックを外したり、場合によってはカテゴリーページを含めても良いでしょう。
※アーカイブページや投稿者ページは特に重要ではないと思われるため、チェックを外しておいて構いません。
他にも“詳細なオプション”として最終更新時刻を含めるかどうかの設定があり、デフォルトではチェックが入っている状態となっていて、クローラーも参考とするため推奨とされています。
Excluded Items(含めないカテゴリーや記事)
続いての“Excluded Items”では、sitemap.xmlに含めないカテゴリーや個別記事を指定することが可能です。
上記の“Sitemap コンテンツ”でカテゴリーを含んだとしても、一部のカテゴリーの記事はサイトマップに記載する必要がない(クロールの必要がない)場合に利用します。

使い方は単純で、sitemap.xmlに記述しないカテゴリーにチェックを入れるだけの設定です。
例えば“お知らせ”といったページはクロールする必要もなく、それよりもっと重要なページを中心にクロールしてもらいたいので除外しておきましょう。
ただし、このサイトマップにはクローラーに対して強制力がありませんので、本当にインデックスの必要がなければ“noindex”を一緒に活用してクローラビリティを最適化します。
他にも、個別ページや固定ページでsitemap.xmlに記述したくないページがあれば、IDをカンマ区切りで複数指定することも可能です。
このIDの調べ方は、投稿・固定一覧ページ上部の“表示オプション”から“ID”にチェックを入れると、各ページの項目にIDが表示され、他にも編集中のurlに含まれる“?post=○○○”の数値がIDに当たります。
Change Frequencies(更新頻度の設定)
ここでは、下記の各種ページについて更新頻度の設定を指定します。
- ホームページ
- 投稿(個別記事)
- 固定ページ
- カテゴリー別
- 今月のアーカイブ
- 古いアーカイブ
- タグページ
- 投稿者ページ
更新頻度はそれぞれ以下の項目から選択し、更新頻度が高いということはクローラーも巡回すべきと理解するでしょうし、更新されないページに関しては無駄なクロールを制御することも可能です。
- 常時
- 毎時
- 毎日
- 毎週
- 毎月
- 毎年
- 更新なし
そしてこの項目では、下記画像にも記載されているようにあくまでクローラーに対する命令ではなくヒントとなるもので、“毎時”と指定したからといって1時間おきに必ずしもクロールされるというわけではありません。

優先順位の設定 (priority)
そして、最後の項目“優先順位の設定”では、0.0〜1.0までの間で優先させたいページを各種設定していきます。
例えば毎日更新するようなブログの場合だと、“投稿ページ”は重要なので“1.0”にしておいたり、更新性の低いページに関しては“0.1”など低く設定しておくことで、上記の“更新頻度”と合わせてクローラーが参考にブログ内を巡回していき、こちらもまたあくまでヒントとなるものなので、デフォルトのままでも問題ありません。
- ホームページ
- 投稿 (個別記事) (“基本的な設定”で自動計算に設定していない場合に有効)
- 投稿優先度の最小値 (“基本的な設定”で自動計算に設定している場合に有効)
- 固定ページ
- カテゴリー別
- アーカイブ別
- タグページ
- 投稿者ページ

ただ、先ほどご説明した項目“投稿の優先順位”で、デフォルトの“コメント数”にチェックを入れたままだと、優先順位“0.2”の“投稿優先度の最小値”が適応されてしまいますので注意が必要です。
コメント数を元に優先順位を考慮しないのであれば、先ほどの項目で“優先順位を自動的に計算しない”にチェックを入れる、もしくは“投稿優先度の最小値”の数値も同じく高めに設定しておくと良いでしょう。ただ、あくまでクローラーのヒントとなるものなのでそこまで気を使う必要もありません。デフォルトのままでも十分であることに間違いなく、強いて言えば“投稿の優先順位”の“優先順位を自動的に計算しない”にチェックを入れるだけでも十分かと思われます。
また、“Google XML Sitemaps”をインストールしたタイミングでsitemap.xmlが自動生成されるわけではありませんので、今すぐサイトマップを作成したい場合は、設定画面の上部に記載されている「Notify Search Engines about your sitemap or your main sitemap and all sub-sitemaps now. 」の“your sitemap”というテキストリンクをクリックします。(手動ではありますが、サイトマップを今すぐ作成することができます。)
サーチコンソールへ送信する方法

sitemap.xmlを作成した後は、サーチコンソールにも情報を伝える必要があります。
送信方法も簡単で、サーチコンソールの「サイトマップ」という項目からsitemap.xmlへのパスを入力して“送信”をクリックするだけです。

あとは自動で“Google XML Sitemaps”がsitemap.xmlを更新し、サーチコンソールがそれを定期的に読み込んでいきます。
ただしこのプラグインは画像ファイルを含んでいません。
そのため、画像検索からの流入も考慮する場合(ページに多くの画像を掲載しているブログなど)、“Udinra All Image Sitemap”といった画像サイトマップ作成プラグインが公開されていますので、そちらと併せて利用すると良いでしょう。
まとめ
今回は、検索エンジンのクローラーにブログ内の重要なページを中心に効率良く巡回してもらうために必要なsitemap.xmlを自動で更新してくれるWordPressのプラグイン、“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”について各種設定や使い方についてご説明しました。
“XML Sitemaps Generator for Google(旧名称:Google XML Sitemaps)”は、ほぼ“有効化”するだけで概ねサイトマップとして機能し、ページが追加されたり更新された際には自動で追記・最終更新日が上書きされ、それをクローラーがヒントとして巡回していくため、クローラビリティといったクロールの最適化にも繋がり、申込みフォームなどインデックスの必要のないページに対しては無駄なクロールを制御することにも期待できるでしょう。
ただし、サイトマップ自体に強制力はありませんので、適宜“noindex”や“robots.txt”などを併せて活用し、クロールの最適化を行うことが大切です。