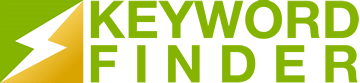検索エンジンの仕組みとは、検索順位が決まる仕組みのことであり、SEOに大きな影響を与える重要なポイントです。
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
というのも、Googleやyahoo!などの検索エンジンは、まずボットと呼ばれるプログラムがwebサイトのページを巡回(クロールするとも呼びます。)し、データベースへインデックス登録します。
その後、検索キーワードに対して相応しいコンテンツが検索エンジンにランキング形式で表示されるわけです。
つまり検索エンジンは、ボットでページをインデックス登録し、いくつもの要素を経て検索クエリに相応しい“答え”をユーザーに返すシステムです。
この検索エンジンのランキング精度を上げる目的で定期的に行われるのが検索アルゴリズムアップデートで、コンテンツを公開する側のサイト運営者は、常にユーザーに役立つ内容を提供し、ユーザーの利便性やユーザビリティを考慮するように注力するべきです。
SEO対策をして検索エンジンに対応してもアップデートで順位は変動します。
ただし、検索エンジンも適当なコンテンツを上位表示させるわけにはいきません。ジャンルによっては専門性や権威性、またはドメインの強いサイトを優先させるケースもあり、記事を制作する際はターゲットキーワードをよく調査することが重要です。
検索エンジンの仕組みと聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと、Webページを定期的に読み込んでインデックス登録し、ユーザーが入力したキーワードに対して適切なコンテンツを表示しています。
そして、この考え方はSEOにも大きく関係し、検索エンジンが評価するコンテンツに対応・対策することで順位を上げることも可能です。
では今回は、検索エンジンの仕組みについて詳しくご説明していきたいと思います。
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
検索エンジンとは?

はじめに検索エンジンとは、Web上にある全ての情報から目的に合ったコンテンツを検索するプログラムであり、Wikipediaでも以下の通り定義されています。
検索エンジン(けんさくエンジン、英: search engine)は、狭義にはインターネットに存在する情報(ウェブページ、ウェブサイト、画像ファイル、ネットニュースなど)を検索する機能およびそのプログラム。
また、検索エンジンはGoogleだけでなく、他にもBingや百度といった検索エンジンサービスもあり数多くの検索エンジンが存在します。ただし日本での検索エンジンシェアとしてはほとんどがGoogle検索が占めているため、検索順位を把握する際はGoogleのシークレットモード(検索履歴に左右されない検索方法)で確認すると良いでしょう。
主要な検索エンジンサービス
- Google(グーグル)
- Yahoo! JAPAN(ヤフー)※現在はGoogleの検索エンジンを利用
- Bing(ビング/マイクロソフト)
- Baidu(バイドゥ/中国)
- DuckDuckGo(ダックダックゴー/プライバシー重視)
- Yandex(ヤンデックス/ロシア)
検索エンジンの仕組み

次に、検索エンジンは以下3つの要素からコンテンツを表示しています。
簡単に言うとWeb上に公開されているページを読み込んでGoogleのデータベースに登録、そしていくつもの要素・評価を経た後に適切なページをランキング形式で検索結果として表示しているわけです。
ここで言う適切なページというのは、ユーザーが検索したキーワードで何を知りたいのか?解決したのか?をピンポイントで詳しくわかりやすく説明した内容を指します。
- クロール
- インデックス
- 検索結果の表示
そのため、検索順位を上げるにはまずインデックスされる必要があり、クロール(ページの巡回)してもらえるように内部リンクを繋いだり、検索キーワードに対して役立つコンテンツを作り込むことがポイントとなります。
それぞれ検索エンジンの仕組み3要素を説明していきます。
クロール(ボットの巡回)
まずGoogleのデータベースに登録されるためにはページを読み込むクローラー(ボット)にクロールしてもらう必要があります。
このクローラーはすでに登録済みのURL、もしくは内部・外部のリンクを辿って巡回していくので、サイト内のどこからもリンクされていない状態である「孤立ページ」だけは避けましょう。
孤立ページのSEOへの影響
孤立ページとは、上述した通りサイト内の他のページからリンクされていないページのことを指します。SEOの観点から見ると、孤立ページは検索エンジンのクローラーが発見しにくくなり、結果としてインデックスされにくくなります。インデックスされなければ、当然検索結果にも表示されず、ユーザーの流入も期待できません。
また、孤立ページが多いサイトは、サイト全体の構造が分かりにくいと検索エンジンに判断される可能性があり、サイト全体の評価にも悪影響を及ぼすことがあります。
【孤立ページの解決策】
孤立ページを防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- サイト内の重要なページ同士を内部リンクでつなぐ
- パンくずリストやカテゴリーページを活用して階層構造を明確にする
- サイトマップ(HTML・XML)を作成し、クローラーやユーザーが全ページにアクセスしやすくする
- 新規作成したページは、既存の関連ページからもリンクを設置する
これらの対策を行うことで、クローラーがサイト内を効率よく巡回できるようになり、全てのページが適切にインデックスされやすくなります。結果として、SEO効果の最大化やユーザーの利便性向上にもつながります。
クロールされない事への対応策
クロールされないということは、いつまで経ってもGoogleのデータベースにインデックス登録されない事から、もちろん検索結果にも反映されません。
また、一度のクロールでサイト内全てのページ・内容を完全に読み込むわけではないので、無駄なクロールを避けるためにもインデックスする必要のないページにはnoindexやrobots.txtで対応しておくことも大切です。(例えば申し込みフォームなど)
要は重要なページを中心にクロールしてもらえる状態が理想で、質の低いコンテンツはリライトで強化する、もしくは削除やnoindexでクローラーを制御することがポイントとなります。
インデックス(データベースへ登録)
次にGoogleのクローラーがページを巡回したらデータベースに登録されるわけですが、無条件で全て登録されるわけではありません。
例えば、明らかに質の低いページやユーザーの役に立たないページはインデックスされませんので、コンテンツの質が重要となります。
この辺りに関しては下記の記事も参考にしてみてください。
他にもURLの正規化を行っていない場合、希に重複コンテンツとして正しくインデックスされないケースも考えられますので、以下のようなURLでアクセスできるなら統一しておくべきです。
以下のURLは全て同じページを意味するわけですが、それぞれインデックスされてしまうと評価が分散されてしまいます。これを防ぐのがURLの正規化なので正しく対応しておきましょう。(後からでも評価を統一できます。)
- https://keywordfinder.jp
- https://keywordfinder.jp/
- https://keywordfinder.jp/index.php
検索結果に表示(ランキング形式)
上記の通りGoogleのデータベースに登録(インデックス)されると、ユーザーがブラウザを通して検索したキーワードの“答え”として適切なコンテンツをランキング形式で返します。
ちなみに正しくインデックスされているか確認するには「URL:(該当するURL)」で検索してみてください。もしインデックスされていなければ、もう少し様子を見るかサーチコンソールからクロールを促してみるのもひとつの手です。
そして、ここで検索結果の上位表示ができていればアクセス数にも期待できますが、検索結果の上位に表示されるためには正しいキーワード選定とその検索意図を満たすコンテンツでなければ上位表示は期待できません。
そのため、インデックスはされている状態だけどアクセスが伸びない場合も十分考えられるので、日々の検索順位を必ずチェックしましょう。
ただし検索順位は200以上もの要素で評価され、さらに最近のGoogleは頻繁にアップデートを繰り返しているので、上位表示を維持するということは非常に難しいことは認識しておいてください。
他にもテーマやジャンルによっては“E-E-A-T”が必要となる“YMYL”といった上位表示が非常に難しいケースもありますので、キーワードの選定や調査は今までよりも重要視されています。
検索アルゴリズムアップデート
検索アルゴリズムアップデートとは、Googleなどの検索エンジンが検索結果の品質向上を目的として、検索順位を決定する仕組み(アルゴリズム)を定期的に見直し・改善することを指します。
これにより、ユーザーにとってより有益で信頼性の高い情報が上位に表示されるようになります。
主なアップデートには、コンテンツの質や専門性、権威性、ユーザー体験(UX)、モバイル対応、ページ表示速度、スパム対策など、さまざまな評価基準の見直しが含まれます。特に大規模なアップデート(コアアップデート)が実施されると、検索順位が大きく変動することがあり、サイト運営者やSEO担当者にとっては常に注視すべき重要なポイントです。
アップデートの影響を受けた場合は、慌てて対策を講じるのではなく、まずは公式情報や業界の動向を確認し、自サイトのコンテンツや構造を見直すことが大切です。ユーザーにとって価値のある情報を提供し続けることが、長期的に安定した検索順位を維持するための最善策となります。
上位表示に必要な要素について

検索エンジンの仕組みを理解することによって上位表示をするにはどうしたら良いのかがわかってきます。
まず、キーワード選定や月間検索数、競合などの調査によって上位表示できるかどうか?参入の余地があるキーワードかどうかを見極めることが重要です。ここで判断を間違うと上位表示できない、上位表示できてもアクセスに期待できないといった状態に陥ってしまいます。
次に、そのキーワードで検索したユーザーは一体何を求めているのか?という「検索意図」をしっかりと理解することがポイントとなり、そのキーワードの意味だけをコンテンツ化しても上位表示することはできないということを念頭に役立つコンテンツを目指しましょう。
この辺りに関しては実際に検索してみて上位表示されているページの内容を把握し、実際に検索ユーザーが求めている内容をチェックすることが大切です。
つまりSEOを理解するには検索エンジンの仕組みを理解する必要があるというわけです。
検索意図を満たしているか
ユーザーは検索したキーワードが持つ意味そのものを求めているわけではありません。
もちろんそういったケースも十分考えられますが、
それよりも断片的なキーワードで何か解決したい物事などを調べている場合が多く、ユーザーはそういった検索キーワードに対する適切な“答え”を探しています。
そのため、ユーザーの求めているものが伝わるページタイトルや冒頭の文章も非常に重要で、検索結果ページから流入しても目次に探している内容がなければブラウザバックしてしまうでしょうし、検索意図が満たされていないことになり、結果検索順位にも影響しかねません。
つまり、検索クエリとコンテンツの関連性を重要視するべきで、この辺りに関してはご自身で判断するのではなく検索結果からユーザーが求めているものを調査していきます。
ただしドメインが強いだけで上位表示しているページもありますので、ドメインも含めよく見極めることが重要です。
質の高いコンテンツかどうか
質の高いコンテンツが重要とは言っても要はユーザーに役立つコンテンツを意味しますから、やはり上記の通り検索意図を満たすことに通じます。
ただ、質として考えると読みやすさだったりぱっと見で理解しやすい内容が好ましく、例えばリスト化や表でまとめたりすると、端的に特徴や比較などを把握できるので、ユーザビリティも考慮すると良いでしょう。
なのでこの場合、検索意図を満たす内容・文字情報の見せ方といった意味合いも考慮する必要があり、スマホで閲覧したケースも想定してPCだけでなく他のデバイスでも読みやすいコンテンツが理想です。
そしてもちろん競合がどのような見せ方をしているのかも参考になりますので、上位表示されている色々なサイトを常に閲覧することもおすすめです。(そのままマネするのはいけませんが、雰囲気や読みやすいフォントサイズ、行間など適度に使用した画像などを注視しましょう。)
これらを考慮すると、細かくわかりやすく説明したコンテンツとなるので、文字数もやや多くなると思いますが、上記の通りリスト化や表にまとめたりと見やすいコンテンツを心がけてください。
サイトマップを作成・送信する
クローラーが巡回する際に参考とするサイトマップ(htmlファイルではなくxmlファイル)もサーバーにアップしておくのも有効です。
サイトマップには優先的にクロールしてほしいページを記載するわけですが、手動だと面倒なのでWordPressをお使いならプラグインで対応すると自動で更新してくれます。(設定画面で巡回しないページを指定できます。)
ただし、このサイトマップはあくまで参考にする程度のもので強制力を持ちません。そのため、本当に巡回してほしくないページがあれば“noindex”などで対応しましょう。
もちろんサイトを立ち上げた初期の段階だとなかなかクロールされない(インデックスされない)ので、まずはサーチコンソールの“URL検査”から巡回を促してみてください。
サイト設計はわかりやすく
クローラーは内部リンクを元に巡回していくので、複雑で深い階層ではなくなるべくシンプルなサイト設計が理想です。
例えばひとつのカテゴリーをさらに細分化する場合、ユーザー目線から使いやすいかどうか?を考慮して判断します。
あまりにも複雑な管理だとユーザーの利便性も悪くなってしまい、同じくクローラーに対してもわかりにくいサイトと認識されてしまう事からクローラビリティにも影響します。(クローラーの巡回は最適化するべきということです。)
つまり、トップページを元にいくつかのカテゴリーを作ってサイトを管理するということはテーマやジャンルを統一するということにも繋がり、そうすることで専門性の高いサイトとしてブランディングの構築も不可能ではありません。
検索エンジンにインデックスされない理由
希に記事を投稿してもなかなか検索エンジンにインデックスされない場合があります。
これにはいくつかの理由が考えられ、まず“robots.txt”で誤って重要なページをブロックしてしまった場合、同じく誤って“noindex”を付けたまま公開してしまった場合、またはあまりにもページの質が低いといったことが挙げられます。
他にも重複したコンテンツであればGoogleの検索エンジンはどれかひとつを優先してインデックスするので、その他は検索結果ページに表示されないケースも考えられます。
要は以下の3点を意識して質の高いコンテンツを常に目指し、クロールしてほしくないページには“noindex”や“robots.txt”で対応するということが重要です。
- キーワード選定
- ユーザーの検索意図
- 役立つコンテンツ
こう考えると検索エンジンは割と単純な仕組みで、ボットでコンテンツを収集してデータベースに格納、その後いくつもの要素を経てランキングとして検索結果ページに返しています。
この辺りを理解することによってインデックスされない理由もわかるかと思いますので、じっくりと対策していきましょう。
まとめ
ここまで“検索エンジンの仕組み”について詳しくご説明してきましたが、改めてその重要性を振り返ってみましょう。
検索エンジンは、ユーザーが入力した検索キーワードに対して最適なコンテンツを表示し、ユーザーの満足度や利便性を高めることを目的としています。そのため、私たちが作成するコンテンツも、ユーザーの検索意図を的確に捉え、分かりやすく有益な情報を提供することが求められます。
また、検索エンジンは日々進化しており、アルゴリズムのアップデートや新機能の追加が定期的に行われています。これにより、検索結果の精度やユーザー体験が向上する一方で、コンテンツ制作者側も常に最新の動向を把握し、柔軟に対応していく必要があります。自社サイトだけでなく、競合サイトの順位や施策も定期的にチェックし、変動の要因を分析することで、今後の戦略立案にも役立てることができます。
さらに、競合の多いキーワードで上位表示を長期間維持することは非常に難しく、検索順位の変動によってアクセス数が大きく左右されることも少なくありません。そのため、複合キーワードやロングテールキーワードを活用し、安定した流入を確保することも重要なポイントです。幅広い視点でキーワードを選定し、多様なユーザーのニーズに応えるコンテンツ作りを心がけましょう。
加えて、検索エンジンの仕組みを深く理解することで、SEO対策だけでなく、コンテンツマーケティングやサイト全体の設計にも応用が可能です。キーワード選定や内部リンクの最適化、ユーザー体験の向上など、あらゆる施策の基盤となる知識となります。
ぜひ今回ご紹介した検索エンジンの仕組みやポイントを踏まえ、今後のサイト運営やコンテンツ制作に活かしてみてください。継続的な学習と改善を重ねることで、より多くのユーザーに価値ある情報を届け、検索エンジンでの上位表示を目指しましょう。