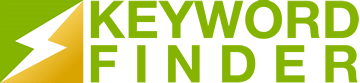自然検索でしっかりと上位表示され、さらに検索ユーザーがじっくりと読んでくれるようにSEOライティングを強化したい…と思っていませんか?
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
昨今のSEOではコンテンツが重要ではありますが、ライティングと言っても難しい言い回しや専門用語を使えば良いか?というと決してそういうわけではありません。
よく文章力を鍛えるといった書籍が多く発売されていますが、どれも難しく書けとは言っていないはずです。
むしろ中学生でも理解できるくらいわかりやすい言い回しの方が“読みやすい”・“良い文章”に強く求められます。
例えば…難しい文章は専門用語も理解しておかなければスラスラと読み進めること自体難しく、さらに膨大な文章量だと最後まで読み終えることなく検索ユーザーは耐えられず飽きて離脱してしまう可能性の方が大きいです。
つまりSEOライティングを強化するということは、“わかりやすく伝える”ことが最も重要であって、ある意味無駄な文言を“削ぎ落とす”作業でもあり、過不足なく有益な情報をコンテンツ化することでもあります。
では、今回は文章力をアップさせる“SEOライティング”について重要なポイントに焦点を当て、考え方など詳しくご説明していきたいと思います。
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
SEOライティングとは
ただ何となく記事を書いてもなかなか上位表示できないように、SEOライティングとは…検索意図を満たすのはもちろん、適宜見出しにキーワードを入れたり検索で上位を獲得させるために最適化させた手法です。
とは言え、単純に文字量を増やすだけでなく、見やすさ・読みやすさを考慮して段落ごとに適宜見出しを付けたり、イメージ画像をはじめ表や図解などをうまく活用して閲覧ユーザーにストレスを感じさせないことが大切です。
また、基本的なSEOを覚えてしまえば後は通常のライティング知識で十分なので、特に難しく考える必要はありません。
ライティング力を上げるための基礎要素

まずはじめにこの記事で説明する“ライティング”とは、主にWebライティングについて考慮しています。
そのため、文章を書く技術そのものも大変重要ではありますが、WebライティングではGoogleの検索エンジンに評価され、検索結果ページに表示されなければ意味がありません。
そしてその次にターゲットとする適切なユーザーへ伝わる文章や直帰・離脱されない工夫、さらにサイトやページが持つ目的(コンバージョン)を果たすための感情の揺さぶりなど、Webライティングに慣れていくためには様々な要素が必要となります。
とは言え…この辺りはライティングだけではなく、Webマーケティング全体の大きな話も関わってくるので、ここではその中のひとつ“集客”や“読みやすい文章”に関して必要なライティングに焦点を当て、ポイントを順に追って説明していくので、検索エンジンに評価され、なおかつ文章力のコツやポイントなどの参考になればと思います。
ターゲット(ペルソナ)を決める
ではまず、誰のためのライティングなのか?ターゲットを設定します。
もちろんガチガチに決める必要もありませんが、Webライティングの場合は基本的に記事を読み終えたユーザーには必ず行動喚起を促すべきです。
そうでなければ、ただWeb上に存在しているだけのページ…広告の意味を果たさない誰が見ても頭に残らない看板のようなもので、当然閲覧ユーザーはそのページに満足することなく検索結果ページに戻り、別のページへと遷移します。
そのため、ページを読み終えた後に行動させるような…“今すぐやらないと”と思わせる感情を揺さぶる言い回しも場合によっては必要となります。
※ページによっては必ずしもコンバージョンさせなければいけないわけではなく、キラーページへうまく誘導することも場合によっては効果的です。
この辺りは書いているうちに慣れるものでもあり常に改善していきたい部分でもあり、多少ライティングに関する書籍や記事を参考にするだけでも上達していくはずです。(特に“人を操る禁断の文章術 | メンタリストDaiGo”は一読してみると面白いかと思われます。)
これを効果的に行うためにもターゲット選定をしておく必要があり、次の項目のキーワード選定にも繋がってきます。
例えば、60代の方がよく検索するキーワードで集客したユーザーに20代向けの商品を勧めるようなもので、わかりやすく伝わるライティングとは誰に向けてのものなのかを明確にする必要があるということです。
SEOライティングのキーワードを決める
続いてキーワード選定を行います。
これは、どのようなキーワードで検索上位に表示されたいのかを考えます。
もちろん、単ワードなどの強いキーワードだと競合も多いため、なかなか上位表示することができません。
この場合は複合キーワードといった複数のキーワードからなる検索ワードを設定して上位を狙います。
また、今回はライティングについて重みを置いた内容にしたいと思いますので、この辺りについては割愛しますが、1記事で上位を狙うのか?それともサイト全体で上位を狙うのかで戦略が異なりますので、“特化ブログ”と“雑記ブログ”の違いや、実際に良さそうなキーワードで検索して競合をチェックし、勝てそうかどうかを判断してみると良いでしょう。
評価されているページの確認
続いて上記で決めたキーワードを実際検索してみて、どのようなページが評価されているのかをチェックしてみましょう。
というのも…設定したキーワードを元にご自身なりにライティングしてもなかなかうまくいきません。(検索結果に上位表示させることができません。)
検索順位は検索キーワードに対する適切な答えを返しているとも言えます。そのため、このキーワードで検索するなら欲しい情報はこれだろう…とご自身で判断するのではなく、キーワードに対する需要は潜在・顕在含めてユーザーが元となり、サジェストも考慮した上で検索エンジンが判断しているためです。
つまり、伝わるライティングに慣れるためには、正しいターゲットユーザーに適切な内容を届けるということでもあり、例えば「A」を知りたいユーザーに「A’」を伝えてもユーザーは100%満足できないでしょう。
これを合致させるためにも検索キーワードに対して必要な“評価されているコンテンツ”や“必要なコンテンツ”の内容・傾向をしっかりと調査することが重要となるわけです。
ライティングを進めるにはしっかりとした下準備が必要ということですね。
検索クエリに対する需要を調査
上記のように検索キーワードが決まったら、実際に検索してみて競合やコンテンツ内容・傾向をチェックしてみるわけですが、それ以外にもなぜそのキーワードで検索したのか?“検索意図”を深く調べる必要があります。(もしかしたら検索ユーザーも気付いていないワードがあるかもしれません。)
それは単純に検索結果とその内容だけでなく、サジェストやYahoo!知恵袋などを参考に(他にもSNSで使用されているハッシュタグなど)どういったキーワードを用いて悩みを解決しようとしているのかを細かく見ていきます。
例えば…「ギター 初心者」と検索した場合の検索意図とは、“選び方”や“練習方法”はもちろん…
- 始めるために必要な機材
- コードの押さえ方や種類
- ピックの持ち方やストロークの方法
- Tab譜の読み方
といった内容になるかと思われます。
そしてこのコンテンツにかなりニッチとも言える上級者向けの内容をいくらわかりやすくライティングしたところで、ターゲットユーザーには響きません。
こういった検索意図から外れたライティングをしていると、いつまでたってもターゲットキーワードで検索結果に表示されることはありません。
キーワードを因数分解する
対策キーワードが決まり、求めるコンテンツ・需要をしっかりと調査した後は、そのキーワードを順序立てて説明するためにまず必要なブロックに分けます。
これは様々な記事を見てみるとわかるように、ページタイトルがあり、その後小説のように最後まで長々と文字だけで間も空けずにライティングしませんよね?
つまり検索キーワードを事細かく(広くという意味ではなく)説明するためには、しっかりと調査した需要(検索上位に必要な各要素)と、緩急付けた“間”が必要となります。
これはライティングと検索エンジン対策ともに共通して必要なもので、“読みやすさ”と“リズム感”を考慮することが重要です。
この辺りはよく“起承転結”など文章のまとまりを示すライティングなどの方法が紹介されていますが、必ずしもこれに当てはめる必要もなく、要はユーザーが知りたい情報を道筋立ててわかりやすく説明していくことを念頭に置きましょう。(段落要素の順番を入れ替えただけで検索順位が改善されたケースも珍しくありません。)
SEOライティングのポイント
これで、ライティングする下準備が整いましたので、続いては記事の構成について考えていきます。
構成と言っても、上記のターゲットキーワードに対する適切なコンテンツをブロック要素ごとに分解し、それをどのような順番で説明していくのか?といったことをユーザー目線で考えていきます。
それはターゲットキーワードに関する疑問や問題などを結論とともにピックアップし、少しずつその理由を信憑性の高い一次情報などのソースや場合によっては権威あるページから一部抜粋といった正しい引用も使い、紐解いていくように順序良く組み立てていきます。
ここでのポイントとしては見出しタグ(主にh2とh3、場合によってはh4)の主従関係・カテゴリ関係を考慮した上で入れ子のようにして仮決めして配置していきます。
※h1タグは記事上部のタイトルに使用します。(head内に記述するページタイトル:<title>タグとはまた別)
例えば…「B」の説明がないと「C」の意味がすんなりと理解できないのに先に「C」をしっかりとライティングしてしまった場合、ユーザーは理解するまでに何度も読み直さなければいけません。
こういった順序を考慮して構成を考えていくわけですが、注意点としてはあまりにも内容を網羅し過ぎない(脱線し過ぎない)という点です。
それは、下記の記事でも非常にわかりやすくご説明されているように、あまりにも網羅したライティングというのは…風邪をひいている方に分厚い医学書を渡すようなもので、この場合本来必要としているものは“今年流行している風邪の傾向と早く治す方法”といったピンポイントに絞ったコンテンツをわかりやすくライティングするべきです。
今まではこの解決策が「長文」と考えられていましたが、ウェブの本質を考えると、それはないだろうというのが私の考えです。私がよく使う例えですが、長文は「風邪ひいたユーザーに対して、医学書を渡すようなもの」だと思います。
ページタイトルを決める
ではまずはページタイトルを仮でも良いので決めていきます。
特にWordPressをお使いの場合だと、管理画面の“記事タイトル”と記載されているところがページタイトルにも使用され、h1にもなります。(分けて指定することも可能です。)
ここではライティングの内容をしっかりとユーザーと検索エンジンに伝えるために対策キーワードを入れたわかりやすいタイトルにすることが大切です。
また、実際に検索結果を見てみるとわかるかと思われますが、多くのケースで左側に重要なキーワードが配置されていると思われます。
このような現在の検索エンジンの傾向を参考に同じく左側に重要なキーワードを置き、長いタイトルだと様々なキーワードも含まされてしまい…何に関するコンテンツなのか?テーマが薄まってしまう可能性も考えられますので、なるべく簡潔に設定することを意識しましょう。
導入文は重要
続いて導入文からライティングを進めていくわけですが、Webライティングの場合、検索ユーザーは答えや解決方法などを早急に見つけたいと思っています。
そのため、望んでいる答えがその先に記載されているかどうかわからないままじっくりと読み進めてはくれません。
そして、先ほど“起承転結”と言いましたが、まず冒頭にある程度の“結果”や“事実”を持ってくることによって、その先に何が詳細に書かれているのか?そもそもこの記事はどういった内容なのか?がわかりますので、せっかく訪問してきた検索ユーザーに直帰されずに読み進めてもらうためにも“読み進めたい”と思わせる導入文を用意しましょう。
例えば…サーチコンソールを参考にしてみると検索順位は低いのにクリック率が割と高めなキーワードが稀に見つかるのはそういった適切なコンテンツが上位表示されているページの中に用意されていないことが原因で、検索ユーザーは満足することなく2ページ目、3メージ目と検索行動を繰り返していることを意味します。(その検索キーワードを元にコンテンツを追加することで順位は改善すると思われます。)
ましてや目次にキーワードを含んだ要素がなければ直帰する可能性も高まりますので、まずはページタイトル、そして導入文となる最初のライティングに読み進めるだけの価値があるかどうか?ストレートに伝える必要があるわけです。
つまり導入文には、ある程度要点がまとめられた内容を冒頭に記載して、何について書かれている記事なのかを明確にするべきです。
ライティングがいくら上手くても読んでもらえなければそこに価値は生まれません。しっかりとユーザーに“読み進めたい”と思わせるだけのポイントを押さえた上で導入文を作り込んでいきましょう。
タイトルタグや見出しにキーワードを含める
最近の検索エンジンにはあまり効果的と言えませんが、ユーザー目線で言うとタイトルや見出しは当然わかりやすくするべきなので、あくまで自然になるようにキーワードを含んだタイトルや見出しにしましょう。
希にほとんどの見出しにキーワードを入れているページを見かけますが、だからといって上位表示できているわけではありません。
SEOには他にも様々な要素が影響して検索順位が決まりますので、ぱっと見で内容がわかる利便性の高いコンテンツが理想です。
読みやすさを考慮する
上記で、ライティングするべき内容をブロックごとに分け、それぞれはじめに仮見出しを付ける理由には、ライティングしている途中で話を脱線させないためであり、書くべき内容を先に決めることで考えがまとまるからです。
これをページタイトルだけを決めてライティングしはじめてしまうと、時間もかかってしまいますし…書くべき内容もその場で考えるため話が脱線してしまい、最終的に何の記事なのか?わからなくなってしまいます。
さらに、ライティングする際に考慮したいのが当然“読みやすさ”です。
これはざっと挙げただけでも以下のような項目が考えられ、中でもリスト化できるところはまとめてしまった方がユーザーにとってもぱっと見で理解しやすく文章自体もすっきりします。
- 箇条書きにする
- 語尾に気を付ける
- 適度な改行を入れる
- “です・ます”、“だ・である”を統一する
- 校正・推敲する
- 句読点の数にも気を配る
- 重要なポイントの箇所はcssで工夫する
- マーカーは必要最小限に
要は…ぱっと見の余白や間を考慮することによって、読むストレスを最小限に抑え、流れるようにスラスラと読み進めることができる文章が理想と言えるでしょう。
最近のSEOは文字数が重要視されなくなっているので、あくまでコンテンツとして過不足なくすっきりと見せるライティングを意識し、関連するコンテンツ群によって内部リンクで強化していくべきです。
※その代わりひとつずつの記事は狭く深く掘り下げた内容が必要となります。
臨場感を意識する
また、わかりやすいSEOライティングとは、イメージしやすい文章も求められ、その場の臨場感を言葉豊かに表現する擬音語など…いわゆる“オノマトペ”も含めるとより伝わりやすくもなり、ユーザーもつい読み込んでしまうかもしれません。
この辺りは競合との差別化を計るためのものでもあり、単純に「美味しい」という言葉ですらいくらでも広がりを持たせることができますよね?この場合むしろ「美味しい」という言葉を使わずにその「美味しさ」を伝えることができればユーザーはもはやそういったイメージができているはずです。
このように同じような内容を書くよりも、よく一緒に使用される頻度の高い単語を意味する共起語なども考慮して単調にならないようなライティングを意識しましょう。
これは、様々な書籍や雑誌などの文字を読むことによる多少の語彙力なんかも必要となってきます。決して難しい言い回しをするという意味ではなく、わかりやすく・丁寧に・詳しく伝えるという意味です。
例えば難しい専門的な内容であったとしても、それをわかりやすく説明するのがライティングの肝でもあり、うまく例えを使って比喩しながら優しく噛み砕きながら説明していきます。
そのため、ある程度の文字量も必要となり、現在でもまだジャンルによっては長文SEOも強い傾向ではありますが、いずれその傾向も変化する時が訪れるかと思われますので、無駄な言葉を極力減らした内容の濃いライティングが求められます。
まとめには行動喚起を考慮する
最後のまとめには、これまで詳しくライティングしてきた内容を改めて簡潔におさらいし、検索キーワードに対する適切な改善案や方法を行動喚起といった意味も含めて後押しします。
というのも、最後まで読んでくれたユーザーはその記事に対して信頼している証拠でもありますので、商品購入や会員登録などのコンバージョンに関してはCTA(コールトゥアクション)を用いて多少大げさにアピールしても恐らく強くセールスされているとは感じません。
※“CTA”とは、記事を最後まで読んでくれたユーザーに対して行動してもらいたい内容をページ最下部に置く導線などを意味します
そのため、“まとめ”とは言っても気を抜けない箇所であり、せっかく読み進めてくれたユーザーをコンバージョンに繋げられずに取りこぼしてしまう可能性すらありますから、大げさにセールス感を出す必要はありませんが、うまく共感を得て感情を揺さぶること、メリットではなくベネフィットへ変換させることが重要となります。
それ以外にもページの特性として、なかなかコンバージョンに繋がらない検索キーワードでライティングを行う場合もあります。(特定のページの順位を上げる、または導線ために必要な関連コンテンツなど)
そういった場合でも、成果となるページへうまく誘導させるライティングが大切で、集客ページとコンバージョンさせるために必要なページの棲み分けを考慮した上でサイト内導線を最適化していけば良いでしょう。
SEOライティングの注意点
ライティングにおける注意点とは、上記で挙げたような内容とも一部重複しますが、まずなんと言ってもキーワードを絞るということが前提で、特にSEOライティングの場合は検索エンジンに評価される必要がありますから、あれもこれも詰め込んだ内容だと何についての記事なのか検索エンジンも評価することができず、検索クエリに対する適切なページとして上位表示させることができません。
さらに、100人が同時に似通った内容や、誰もが知っているような内容をライティングしても上記と同じく評価することができない・価値がないため(ライティングのみを考慮した場合)、1ページ1キーワードに絞って深く掘り下げた内容が評価される傾向にあるということです。(※文字数・単語数が多ければ評価されるというのと全くイコールにはなりません。)
そのため、なぜそのキーワードで検索したのか?需要やニーズをしっかりと調査する必要性・重要性がわかるかと思います。
ではライティングに必要なポイントを注意点も含めていくつか挙げていきます。
具体例や事実となる証拠を明示する
まずはこれですね、全てに裏付けとなる根拠をつけるという点です。
これは、扱うキーワードによっては誰もが知っているレベルの内容から信頼できる情報なのかどうか?様々あり、場合によっては証拠となるソースが必要となるケースがあります。
例えば…“友人から聞いた話ですが~”や、“〇〇らしいです。”といった言い切らないあやふやなライティングだと検索ユーザーは信用できません。
これだと単なる噂話で終わってしまい、行動喚起を促すことも難しくなってしまいます。
これは、先ほどもご説明した検索キーワードに対する需要・ニーズの調査不足が徹底的な原因となります。
そのため、ライティングで最も強いのは実体験を元にした内容です。
これだと信憑性も高まりますし、写真なども活用することによって他にはないオリジナリティが生まれます。
つまり、ライティングを進めていくに当たって、証拠を表記する必要性があるのなら、一時情報や権威あるサイトから正しい引用表記によって一部抜粋して信頼性を担保することが重要となるわけです。(引用に関しては念のため各サイトのポリシーなどを確認してみてください。)
ここにご自身なりの見解・意見をライティングすることによって競合との差別化にもなりますし、オリジナルコンテンツにもなります。
スマホでの見え方にも考慮する
続いては、ライティングした記事が各デバイスごとによってどのように表示されているのか?という点で、全ての検索ユーザーがPCを利用して閲覧しているとは限りません。
また、最近はスマホからの検索の方が多い傾向にありますので、特にスマホでの見え方にも気を配るべきです。
PCの場合だとちょうど良い行数でもスマホの場合だと窮屈に感られる場合もありますので、テンポ良く読み進めてもらうためにも文字サイズも含めて一度スマホからチェックしてみてください。
改行を入れる
これは当然ですが、1つの段落の中でも句読点「。」の後には改行を入れると窮屈な印象もなくなり、読みやすいランディングにも繋がります。
また、段落とは基本1文字空けて書き始めますが、SEOライティングの場合は1文字空けるよりも段落と段落の間に“余白”を入れることによってより一層見た目としての読みやすさがぐんと上がり、1段落=1つの内容としても伝わりやすくなるため、改行と段落を内容によってうまく使い分けて活用してみてください。
他にもライティングのコツとして、同じ文末を繰り返さないという点も重要で、例えば…文末が「です。」が5つほど繰り返している文章を想像してみてください。
この場合、どうしても文章が単調になりがち(日記風)で読みにくさにも繋がってしまい、その結果伝わりにくくなってしまいます。
この辺りを考慮して、文末の「です・ます」はもちろん、他にもいくつかのバリエーションを考え、場合によっては“名詞”などで文章を終わらせる“体言止め”なんかもちょうど良い文章のアクセントとなりますので、はじめから強く意識する必要はありませんが…推敲する際に色々なパターンを考えてみて、使用してみるのもひとつの手です。
推敲する
一通りライティングを終えた後は、文字校正なども含め何度も推敲(すいこう)し、文章をよりわかりやすくブラッシュアップしていきます。
例えば文章の助詞を意味する“てにをは”に関しては、ちょっとした違いによって伝わり方・印象が変わってきますので、もっと簡潔に伝えることはできないか?といった点を意識して何度も推敲を重ねていくとすっきりとした言い回しをすることもできるようになります。
そのため、ライティングの最後には必ず文法を校正する・誤字脱字の見直しなど、文章を削ぎ落とすつもりで必要のない箇所を削除、またはまとめるなどの推敲という作業が必要となります。
この作業は何度もライティングした内容を読み直す作業となりますので、校正・推敲するためのツールを導入してみても良いかもしれません。
文章が書けない場合
ここまで読んできて、ライティングに必要なのはわかりやすく伝える方法と慣れることだということがおわかりいただけたかと思われます。
すなわち、はじめのうちはとにかく書くことです。
先ほども少し触れましたが、以下のようなポイントを押さえた上で100記事ほどライティングをしていると書き終えた頃にはその100記事を見直すことで、修正点がかなり多く見つかるはずです。
- ペルソナに沿ったキーワード選定を行う
- 競合・コンテンツの内容をチェックする
- 適宜ふさわしいページタイトル・見出しを付ける
- 詳しく書き、推敲によってさらにわかりやすく書く
それでもターゲットとするキーワードで順位が付かない…といった場合は、年代や性別によっても使用するキーワードや言い回しは異なり、ライティングそのものもターゲットに響く内容が異なる場合があるため、改めてターゲットとキーワード、そしてそれに対する答えとなる内容調査を行ってみます。
つまり、検索キーワード=ユーザーが求める内容・検索意図=Googleが評価するコンテンツといった考えが重要で、あくまでユーザーが求めるものかどうかはGoogleが判断しているため、うまく検索順位が付かない…順位が上昇しないといった場合の多くはここが合致していないケースが多いと思われます。
そのため、しっかりと検索エンジンに評価されている傾向を掴み、ポイントを押さえた上でそれ以上のコンテンツを作り込む必要があるというわけです。
あとは、ライティングに慣れるためには読書することも必要で、恐らく多くのトラフィックを集めている(思い通りのキーワードで上位表示させることができている)ブロガーの中で、読書をしていない方はいないかと思われます。
これは上手い言い回しや語彙力を高めるため以外にも、例えばなぜか読みにくい…または凄く読みやすいと感じる文章が少なからず出てくるはずで、なぜそう思ったのかをしっかりと考えることによってSEOライティングは徐々に上達していきますので、常に何らかのインプットは欠かさず行った方が良いでしょう。
まとめ
今回は、検索順位を考慮したSEOライティング中心にコツやポイントを押さえた“ライティング”の基礎について詳しくご説明しました。
このようにライティングとは、特に難しい知識が必要というわけではなく、書いて慣れていくものであって、それと同時に書く内容をしっかりと調査することが重要となります。
よく内容を知った上でライティングするということは、話しながら書くということにも繋がり、それはつまりわかりやすい・伝わりやすい文章となるはずです。
これを調べながら書くという作業を行ってしまうと…場合によってはただコピペ・リライトしている価値のない記事にもなりかねません。しっかりと事実関係を調査・知った上でご自身の言葉でライティングし、事実を証明することが必要なら場合によっては信頼できるサイトからの正しい引用を用いて信憑性を担保し、ユーザーからも支持される内容、そして読みやすい文章を目指しましょう。