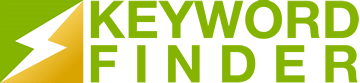Googleサーチコンソールとは、サイト内のユーザー行動をチェックするアナリティクス(GA4)とは若干異なり、サイトに流入してきた検索クエリやその検索順位、表示回数やクリック数などを把握するSEOツールです。
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
例えば登録したサイト内の状況(各ページの流入キーワードや順位)をはじめ、検索結果の状態をチェックできるため、SEO対策を行うには必須とも言えるツールとなります。
他にもページのインデックス状況やHTMLエラー情報、集客キーワードとページなども確認でき、2018年にリリースされた現在の新サーチコンソールを使うことで、集客キーワードとページ情報をより詳細に把握できるようになりました。
特にSEO対策では現状を把握しておくことが重要なので、集客できていないページの流入キーワードやその順位などをチェックして強化していくといった活用方法が主に挙げられます。
では、今回はSEO対策に役立つ“サーチコンソール”について使い方やポイントとなる見方などを詳しくご説明していきたいと思います。
\ 短期間でアクセス数を増やす専用ツールをご案内!/SEOツール「キーワードファインダー」を無料で見る
サーチコンソールとは?
サーチコンソールは、アナリティクスよりもUIが割とシンプルで重要なポイントも限られているため、比較的使いやすいSEOツールであり、以下の通り検索エンジンに登録されているサイトの各ページに関する状態が把握できます。
Google Search Console は、Google 検索結果でのサイトの掲載順位を監視、管理、改善するのに役立つ Google の無料サービスです。
そういった状態を把握することによって検索順位を改善することに繋がり、アナリティクスと同じくSEO対策には欠かせないツールというわけです。
特に最近では、数多くの集客よりも購買意欲の高いユーザー(コンバージョンしやすいユーザー)を増やすことが重要ということもあって、複合キーワード(ロングテールキーワード)と呼ばれるワードでの対策が主流となっています。
そこで現在の順位を少しでも改善することに役立つサーチコンソールが重宝されているというわけです。
サーチコンソールの使い方
サーチコンソールのメニューには主に以下の項目があり、流入キーワードとその順位を調べたり、正しくインデックスされているかどうか?重複やリダイレクトがどれくらい存在するのか?などのインデックス状況、そして“Core Web Vitals”と“HTTPS”に対応しているページ数などをチェックできます。
- 検索パフォーマンス
- インデックス作成
- エクスペリエンス
他にもページ毎の状態をチェックする“URL検査”やパンくずリスト、手動による対策やリンク状況まで把握できます。
このように主にサーチコンソールとは、ページのインデックス状況をチェックするツールと覚えておけば良いでしょう。
URL検査
まず新しくなったサーチコンソールにはクローラーの巡回を促す“Fetch as Google”といった項目がありません。
これは新しく“URL検査”という項目に集約されていて、どの項目を見ていても管理画面上部に表示されている“「(ドメイン名)」内のすべてのURLを検査”と表示されているフォームに、インデックスさせたいURLを入力してエンターを押します。
すると、下記のようにページの状態が表示されます。
そして、この場合、“インデックス登録をリクエスト”をクリックすることで、今までと同じく、クローラーの巡回を申請することができます。

まだページがインデックスされていない場合も、同じく“インデックス登録をリクエスト”といったリンクが表示されるので、そちらをクリックすることで、クローラーの巡回を促すことが可能です。
ただ、本来はページの状態を調べる項目なので、もしインデックスされていない場合などに問題がないかこの項目でチェックしてみてください。
検索パフォーマンス
続いて左メニューから“検索パフォーマンス”へ進みます。

上記画面に表示されているのは、選択したサイトが過去3か月でどのくらい自然検索で流入したのか、キーワードごとの順位や表示回数、そしてCTRといった検索結果に関する数字です。(現在は“検索パフォーマンス”の中に“検索結果”という項目がこれに当たります。)
デフォルトでは、ドメイン全体・期間3ヶ月が設定されていて、ここにクエリ・ページ・国・デバイスを適宜指定し、さらに期間を指定することで、いつ、どのようなキーワードで流入していたのか推移の変化などを詳細に確認することができます。
また、ここでの日付指定は、以下のようにフィルタ:7パターン、比較:8パターン用意されていますので、適宜期間を指定して集客していたキーワードを確認してみましょう。

特に期間の“比較”は、ページごとのトラフィックが増減した時に参考になるのではないでしょうか?
ページ毎に確認する
上記では、サイト全体の流入キーワードに関するものが一覧表示されていましたが、これを個別で見ていきたいと思います。
特にリライトによって効果を最適化させるためには、個別にどういったキーワードで順位が付いているのかを把握しておくことが重要です。
そして、それを元にユーザーが求めているものをチェックし、コンテンツに足りないものを充足・または不要なコンテンツを削除することによって、より順位上昇に期待できるため、しっかりと調査しておきましょう。
まずは“ページ”タブをクリックします。

そして、確認したいページをクリックして、再度“クエリ”に戻ります。
すると、ページが絞り込んだ状態となって個別ページに流入している検索キーワードをチェックできます。

また、ここではキーワードに対する検索結果での表示回数、クリック数がデフォルトで表示されていて、グラフの上にある“平均CTR”と“平均掲載順位”をクリックして選択すると、各ページに項目が追加され、詳細を確認することができます。
流入キーワードをコンテンツに活用する
現在のSEO対策は、1ページ1キーワード(複合キーワード含む)に絞って対策を行った方が順位が付きやすい傾向にあります。
というのも、検索ユーザーのニーズに答えるためには、コンテンツを網羅的に枝分かれするべきではないからであって、ひとつのテーマを説明するためにサブコンテンツ、さらにサブのサブコンテンツといったページ構成では、検索エンジンも何についてのコンテンツなのか伝わりにくくなってしまうからです。
そのため、サーチコンソールの上記画面で以下のような傾向があれば、コンテンツの部分的削除を考えてみると良いでしょう。
- 様々なキーワードで流入している
- 想定外のキーワードで流入している
こういった場合、削除したコンテンツはそのテーマをページタイトルにして別ページを作り込み、内部リンクで繋げることによって専門性の高いサイトを構築することができます。
Discover
Discoverとは、Googleが提供する無料アプリ“Googleアプリ”内にご自身の好みに合わせた情報コンテンツがリスト形式で表示される機能です。
この機能の検索パフォーマンスがサーチコンソールで確認できます。
インデックス作成
次に“インデックス作成”というタブの中には“ページ”・“サイトマップ”・“削除”といった項目があり、それぞれ文字通りインデックスされているページの数やサイトマップの状況、さらに一時的にページを削除したい場合に便利な要素が並びます。
ページ
まず、以前“カバレッジ”といった名称から“ページ”へ変更となった項目では、登録してあるサイトのインデックス状況を簡単にチェックできます。
そして、チェックできる内容は以下のような要素に分かれていて、正常なインデックスを意味する“有効”や、何らかのエラーが原因でインデックスされていない“エラー”、そして意図的にインデックスされていない正常な状態を意味する“除外”といった様々なインデックス状況を確認できます。(例:“送信されたurlにnoindexタグが追加されています”など)
- エラー
- 有効(警告あり)
- 有効
- 除外
その項目名から何を意味するのか少しわかりにくいと感じている方も多いかもしれませんが、要は公開しているページの中には、何らかの理由から“noindex”の付与によって検索順位に表示される必要のないページもあり、そういったページには当然クロールの必要もありませんから、エラーを改善することによってクローラビリティにも繋がるわけです。
そのため、ここでは主に正しくインデックス数が増えているか?(記事を投稿した分)または何らかのエラーによってインデックス削除されていないかどうか?といったチェックを簡単に行うことができ、旧サーチコンソールでの“インデックスステータス”よりもさらに管理しやすくなったと言えます。
サイトマップ
こちらは、旧サーチコンソールから継承された“サイトマップ”で、更新したXMLサイトマップを簡単に送信し、検索エンジンにその内容を伝えることができます。
また、送信済みの場合は以下の内容を瞬時に確認することができ、サイトマップが正しく更新されているかどうか?ページが認識されているかどうかなどサイトの状態などを定期的にチェックする場合に役立ちます。
- 最終読み込み日時
- ステータス
- 検出された URL
これによって、より詳しくページの状況を調べることができるため、ここを参考にエラーやインデックス状況を定期的にチェックすると良いでしょう。
削除
この項目では一旦インデックスから削除したい場合に利用します。
利用方法は「新しいリクエスト」をクリックし、直接URLを入力して“次へ”をクリックするだけです。
例えば古いページを別ページとして新たに公開する場合や間違った情報を公開してしまった際、すぐに削除したい場合に活用してみてください。
ただしこの“削除”では一時的な削除となりますので、その後必要であれば“noindex”にしたりページそのものを非公開にするなどの対応を行いましょう。(6ヶ月後に再度インデックスされてしまう可能性があります。)
エクスペリエンス
“ページ エクスペリエンス”では「Core Web Vitals」と「HTTPS」の状況が確認できます。
詳細は“ウェブに関する主な指標”と“HTTPS”の項目をチェックしてみてください。
まず“ページ エクスペリエンス”ではざっくりとした概要が表示されていて、“ウェブに関する主な指標(Core Web Vitals)”と“HTTPS”について改善が必要か良好な状態なのかが瞬時に把握できます。
特に“ウェブに関する主な指標”ではモバイルとPCで分けてチェックできるため、SEOに重要なモバイルを中心に見ると良いでしょう。
また、“良好な URL と判断されなかった理由”も表示されるので“改善が必要”とされるページがあれば適宜対応してください。
“HTTPS”に関しては文字通りSSLに対応しているページがどれだけあるかチェックできるだけです。
拡張
次に“拡張”には、“パンくずリスト”の項目以外にもページに実装してあれば“よくある質問”や“サイトリンク検索ボックス”という項目があります。(表示されていないアカウントもあります。)
そして“パンくずリスト”では検索エンジンが認識しているページ毎のパンくずリストが表示され、問題があれば“無効”としてカウントされているはずなので適宜対応しましょう。
また、FAQ形式の構造化データをページ内に埋め込み、正しく検索結果にリッチリザルトとして表示されていれば“よくある質問”の項目にページ数が表示されます。ただ、実装してあっても検索結果に必ずしも表示されるとは限りません。
そして、“サイトリンク検索ボックス”とは検索結果にサイト内検索のボックスを表示させるもので、ユーザーの検索行動を楽にすると同時にサイト内検索を行ってもらうことによって確実な流入が見込めるというものです。
ただし実装には構造化データでの記述が必要で、必ずしも表示されるとは限りません。
詳しくは以下の公式ページも参考にしてみてください。
→参考:サイトリンク検索ボックス(WebSite)の構造化データ | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers
セキュリティと手動による対策
この項目には、“手動による対策”と“セキュリティの問題”があり、“手動による対策”では主にガイドラインに違反した際、ペナルティを受けてしまうことによってここに内容が表示されるので、問題箇所を修正して改めて審査をリクエストしてみてください。通常は“問題は検出されませんでした。”と表示されているはずです。
そして、“セキュリティの問題”ではサイトがハッキングされた場合や何らかの攻撃を受けている時に表示されるもので、滅多に表示されることはないかと思われますが、万が一サイトに何か問題があれば正しく修正を行って再審査をリクエストして改善しましょう。(この場合Webページは正しく表示されていない可能性があるので、定期的にチェックしてみてください。)
リンク
続いての“リンク”は独立した項目として表示されていて、外部リンク・内部リンクはもちろん、リンク元サイトや設置されているアンカーテキストなども確認できます。
例えば“上位のリンク元サイト”の場合、気になるサイトをクリックするとどのページにリンクされているのかが表示されるので、さらに気になるページをクリックすると実際にリンクされているページが表示されます。
また、質の低いリンクは検索順位を下げるひとつの要因となるので、定期的にご自身のサイトにどういったリンクが付いているのかチェックしてみて、必要があればリンクの否認を行いましょう。(だいたいのリンクはGoogle側で認識しているので、ほぼ気にしなくても問題ありません。)
サーチコンソールの登録と設定方法
では実際に“サーチコンソール”を利用する方法を簡単にご説明します。
基本はGoogleアカウントを作成し、そのアカウントで“サーチコンソール”にログインするといったイメージで設定画面へ進みましょう。
“今すぐ開始”をクリック
Googleアカウントを作成済みと仮定して、上記のホームに遷移すると“今すぐ開始”といったボタンが表示されているので、そちらをクリックします。
その後、メールアドレス(または電話番号)とパスワードを入力してログインしてください。
プロパティタイプを選択する
次にプロパティタイプ(ドメインかURLプレフィックス)のどちらかを選択してサイトを登録していきます。
ここで“ドメイン”を選ぶ場合は、サブドメインやhttps有無、wwwありなしのドメインを含む全てのURLが計測対象となり、所有権の確認もDNSが必須となります。
一方、“URLプレフィックス”の場合だと特定のサイトのみ計測対象で、所有権の確認も複数選べるので特に理由がなければ“URLプレフィックス”で登録しましょう。
所有権の確認
最後に所有権の確認を行います。
これを行わなければ第三者でもサーチコンソールが登録できてしまいますから、必須の確認となります。
そして上記で“URLプレフィックス”を選ぶと、以下の通り確認方法がいくつかあり、特に“HTMLファイル”での確認方法が一番簡単かと思われますので、ファイルをダウンロードして該当のサーバー(第一階層)にアップロードして“確認”ボタンを押して完了です。
- HTMLファイルのアップロード
- HTMLタグ
- Google アナリティクス トラッキングコード
- Google タグマネージャー
- Google サイトまたはBloggerアカウント
- ドメイン名プロバイダ
まとめ
今回は、サーチコンソールの使い方について特に重要なポイントや登録方法などをご説明しました。
以上のことから、サーチコンソールは登録したサイトに関する検索結果の流入キーワードを中心にページごとの状況を詳しく確認するために非常に便利な無料ツールです。
上位表示させるためには、コンテンツを構築する“キーワード”をチェックし、しっかりと内容を見直す必要があるため、サーチコンソールは欠かせません。
上記を参考に重要なポイントを定期的にチェックして上位表示を目指してください。